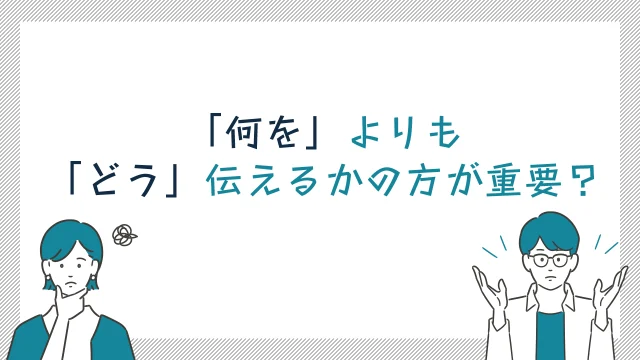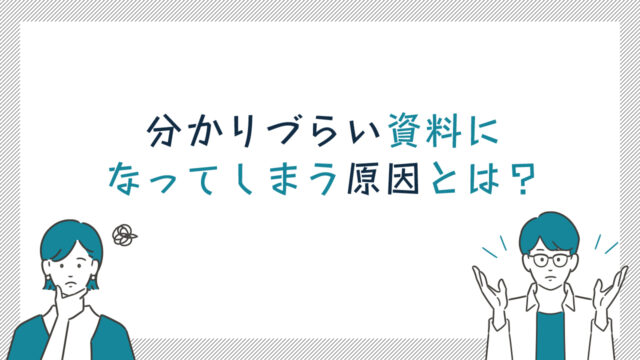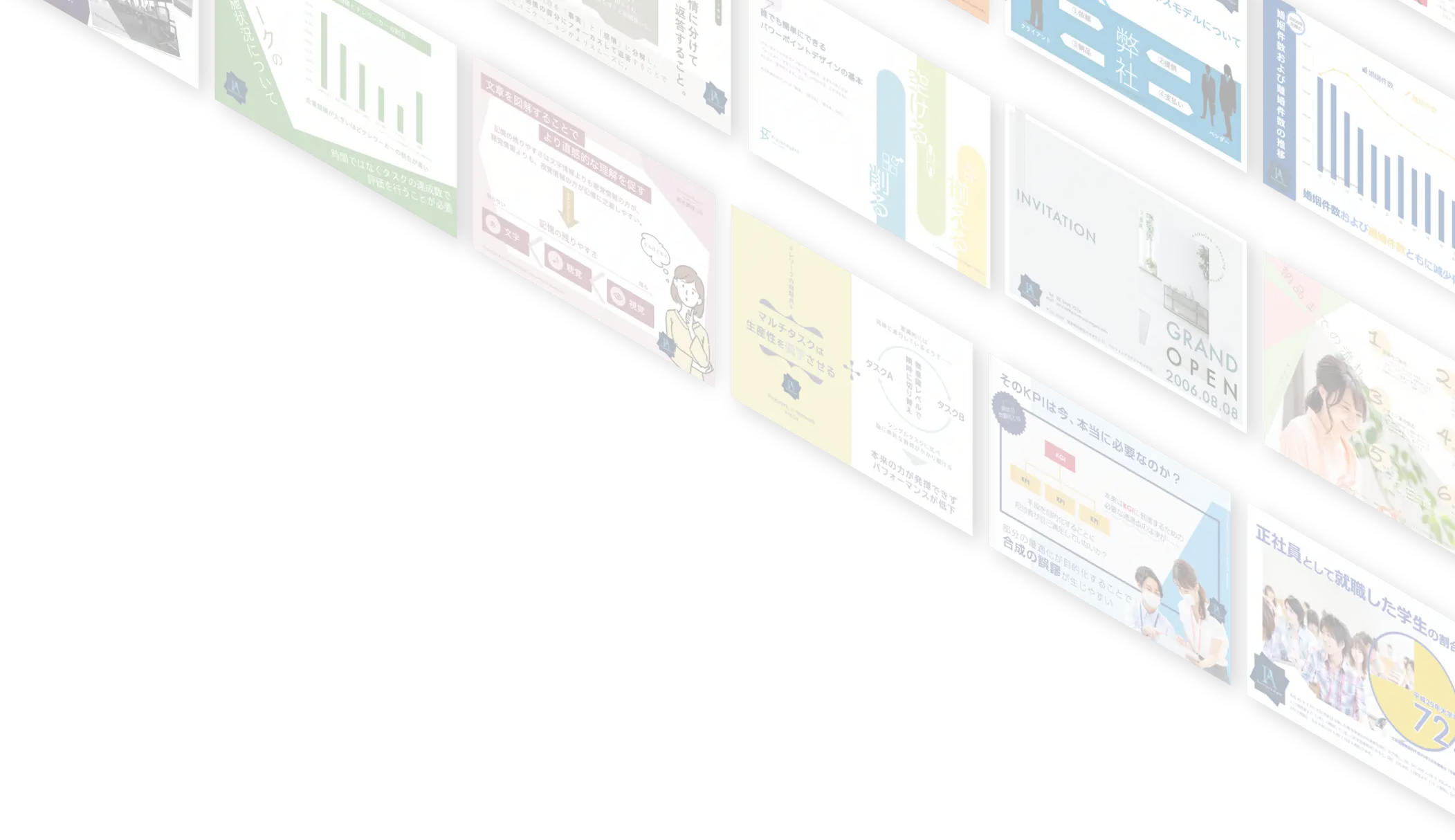

プレゼン原稿の覚え方のコツは
まず覚えやすくしてから記憶する
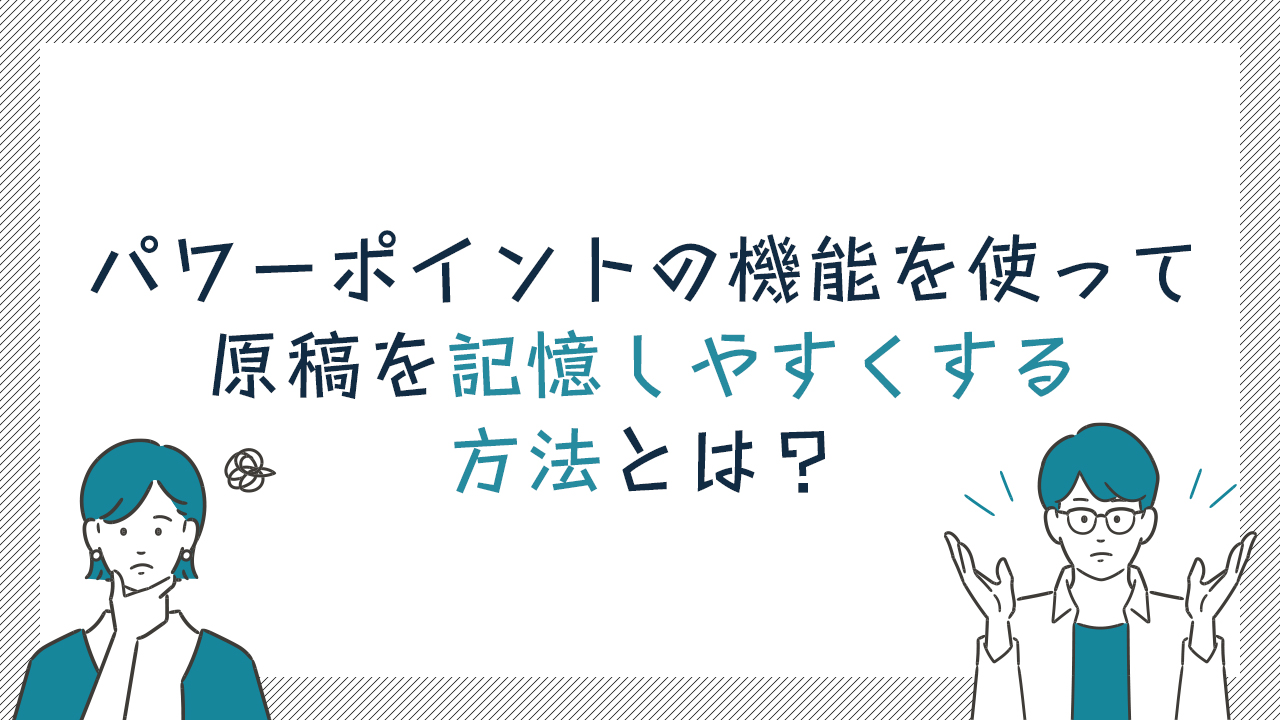
記事の内容
プレゼンで話す内容を覚えるコツ
今度のプレゼン長めだから覚えるのが大変
俺も覚えるの苦手。リアルに毎回テキトーに話してる
普段プレゼンする機会がほとんど無い方はもちろん、慣れている方でも、ここぞって時の大事なプレゼンの時は、話す内容を覚えるのに苦労されている方が多いと思います。
そこでプレゼン内容を覚えるコツを3つご紹介いたします。
それは、
1.プレゼン資料を見直す
2.自分用のトークスクリプトをつくる
3.インプットよりもアウトプットに時間を割く
となります。
この3つのコツを実践するための基本的な考え方は、覚えなければならないことを覚えやすくしてから、科学的に証明された記憶法を使って練習するということになります。
それではそれぞれ具体的な方法を説明していきます。
1.プレゼン資料を見直す
そもそもプレゼン資料は覚えやすい作りになっているでしょうか?
話す内容を覚えにくいのはプレゼン資料に原因がある場合があります。

覚えにくいプレゼン資料とはどのようなものかを仮に桃太郎の話で例えれば、
桃が流れてきて、
鬼退治して、
キジが仲間になって、
おばあさんがきびだんごを作って、
みんなで舟を漕ぐ。
のようなイメージのプレゼン資料です。
話の流れがめちゃくちゃだな
客観的に見れば「めちゃくちゃ」と気づくのですが、これがずっと会社で使ってきたプレゼン資料とかになると、その存在が当たり前のものとなっている可能性があります。
仮に資料の整合性の無さを上司に指摘しても、
「前からこうだから」
とか
「自分はこれで問題無く提案できてるから」
など、前例踏襲的な回答が返ってきて資料そのものの問題にはフォーカスされない場合もあります。
覚えられないあなたが悪いってことになるわけか
また、自分で作ったプレゼン資料でも、
「思いつくことをとりあえず並べました」
「様々な部署の人間が作った資料を寄せ集めました」
「会議で出た色々な意見を折衷してまとめました」
などの場合は、場当たり的な作りになっている可能性が高く注意が必要です。
認知心理学には「精緻化」という概念があります。
これは、情報を深く理解し、関連付けを行うことで、記憶を強化するプロセスのことです。
つまり、ストーリーが曖昧で自分がよく理解できないものは、そもそも覚えにくいということになります。
そうはいっても作り直すの大変だし……
その場合は、スライドの順番だけでも変えてみてください。
自分なりにしっくりくる順番に変えるだけでも、かなり話しやすくなることを実感できるはずです。
当たり前ですが、目の前にあるプレゼン資料だけが、プレゼンする唯一の手段ではありません。
2.自分用のトークスクリプトをつくる
納得のいくプレゼン資料ができたら、自分用のトークスクリプトを作ります。
プレゼンで話す内容を書き起こすイメージです。
一言一句まで毎回同じように話せる必要はありませんが、やはりベースとなるトークスクリプトがあった方が、伝え方が安定することになります。
伝え方が安定すれば、それが繰り返されることになりますので結果、覚えやすさにつながります。
何度も同じようなこと言ってればいずれ覚えるってことね
そのとおりです。
これが毎回思いつくことを話すということになれば、伝え方が安定せず覚えにくいということになってしまいます。
また毎回、伝える内容が大きく変わるようであれば、プレゼン結果の検証を行うのも難しくなります。
毎回伝える内容が変われば結果も当然ブレるよね
そうならないためにも自分用のトークスクリプトをつくることが重要です。
営業成績ナンバーワンのあの人のトークを再現した
『君もデキる!鉄板トークスクリプト』を
会社からもらってるけど
それが「覚えやすい」のであれば問題ありません。
しかし、なんか覚えにくいということであれば、言い回しなどを自分の言葉に置き換えることが必要です。
例えば、他人がつくったトークスクリプトの中に、
「ゆえに、信頼感を醸成することにつながります」
という部分があったとします。
これが使い慣れない言葉であった場合、どうしても違和感が発生し覚えるための障害となってしまいます。
その場合は、
「このことによって、お客様からの信頼を獲得していきます」
など、
自分の中で馴染みのある言葉に置き換えることで記憶しやすくしていくことができます。
3.インプットよりもアウトプットに時間を割く
プレゼン資料とトークスクリプトが覚えやすい作りになったら、後はただ覚えるだけです。
受験を思いだして自分にあった記憶法を試してみてください。
科学的には「アクティブリコール」「テスト効果」「想起効果」などの言葉で知られているとおり、記憶したことを積極的に使うことによって長期記憶化しやすくなる(覚えやすくなる)ということが証明されています。
覚えたことをどんどん記憶から引き出して使う。
つまり、インプットよりもアウトプットに多くの時間を割くべきということになります。
プレゼン内容を覚えるうえで役立つ方法をいくつかご紹介させていただきます。
トークスクリプトをひたすら音読する
記憶は様々な感覚を使って覚える方が定着しやすくなります。
黙読なら視覚を主に使って記憶することになりますが、音読なら視覚のみならず聴覚と触覚(口の動き)を使って覚えることが可能です。
音読によって言葉の流れやリズムを体で覚えることができます。
覚えるってなると黙読しがちだもんね
思いだしながら書き出す
思いだしながらノートなどに書き出すことでも効果は大きいですが、それとは別に試していただきたい方法としてパワーポイントやワードなどの『ディクテーション機能』を使う方法です。
いわゆる「音声入力」のことですが、話した内容がどんどん書き起こされていくことになりますので、自分がどんな内容を話しているのか検証が容易になります。

※ノートの部分に音声入力しているイメージ
スライドを見ながら録音する
パワーポイントには各スライドに音声データを添付するための機能があります。
その機能を使って実際にスライドを見ながら録音することで、スライド画面とトーク内容をリンクさせながら記憶することができます。

※スライド内に音声を録音しているイメージ
プレゼンしている自分を録画する
パワーポイントには録画機能もあります。本来はスピーカーの話している姿をスライド内に映像として表示する機能(PIP:person in presentation)ですが、練習にも活用することができます。
カメラ付きのパソコンであればどなたでも簡単に行うことができますので、プレゼンする自分を客観視して改善を行うためにもオススメの方法です。

※パワーポイントの機能を使って録画しているイメージ
他者に自分のプレゼンを見てもらう
新人の頃は上司や同僚などをプレゼン相手と見立てて、実際にプレゼンを行う「ロープレ」を実施する会社も多いと思います。
しかし、新人とは呼ばれない中堅以上の社歴になってくるとその機会も減ってくるのではないでしょうか?
その場合は、家族や友人などに協力してもらうかプレゼン研修サービスなどを利用するのも手段の一つとなります。

他人に評価してもらう時のポイントはポジティブフィードバックしてもらえるように事前にお願いすることです。
つまり、悪いところではなく良いところを見つけてもらいます。
短所克服よりも長所伸展を目指すことで、プレゼンに対するネガティブなイメージを払拭していきます。
ネガティブなイメージが払拭されれば練習するモチベーションも高まりますので、結果的に短所も克服しやすくなっていきます。
自分らしくプレゼンするのが一番ってことだな
覚えなくてもプレゼンできる環境を作り出す
ここまではプレゼンで話す内容を事前に練習して覚えることを前提に話を進めてきましたが、そもそも覚えなくてもプレゼンできる環境を設定できるのであればそれに超したことはありません。
例えば、リモートでの打ち合わせです。
一時期に比べ出社回帰傾向が強くなってきたとはいえ、クライアントとの打ち合わせはリモートが中心という人も多いのではないでしょうか。
そのため話す内容に不安がある段階ではリモートでの打ち合わせをお願いしてみるのも一つの手段となります。
リモートであればパワーポイントの『発表者ツール』を使って、プレゼン原稿を見ながら話すことができますので、覚える必要がなくなります。
ただ、話者の表情や仕草が見えにくくなる分だけ、対面とは別の難しさが発生します。
そもそも出社回帰傾向が強まっているのも、リモートでは深い意思疎通ができないと考える企業が増えていることが原因となりますので、リモートにするデメリットも考慮したうえで検討する必要があります。
また、使えるシチュエーションが限られるため詳しくは解説しませんが、カメラ前や大多数の聴衆に向けてプレゼンを行う場合は、プロンプターの活用も有力な選択肢となります。
カメラと原稿、聴衆と原稿を同時に見ながらプレゼンテーションを行うことが可能になります。
興味のある方は「プロンプター」で検索してみてください。
資料を読み上げるプレゼンはすべきではない
プレゼンで話す内容が覚えられないまたは、覚えるのが面倒だからプレゼン資料内にすべて話す内容を書き込んで読み上げる人がいます。
これは、基本的にやめることをオススメします。
その理由はあれこれ説明するよりも、YouTubeなどで国会中継に関する動画を検索して見ていただくと明らかですが、紙を見ながら話す人の話は、とにかく頭に入りにくいです。

原因は様々ですが、棒読みになりがちなのと、目線が合わない人の話は集中して聴くことが難しいということがあります。
その他にも、読み上げることに集中することでジェスチャーも減るため非言語情報が不足することも、分かりにくくなる大きな要因となります。
読み上げるだけのプレゼンなら資料を送ってもらえれば済むし
ただし、国会での答弁については紙を見ながら話すことも仕方がない部分もあります。
まず、法律に関する話をしていることが多く、一言一句が変わるだけで意味が変わってしまうため正確性が重視されます。
また、質問を受けてから答弁書を作って回答するまでの時間が限られるため、答弁の練習をしている時間がありません。
これらのことから、国会答弁のような正確性が求められる特殊なプレゼンを除いて、プレゼン資料を読み上げるだけのプレゼンはすべきではありません。
一言一句まで暗記しようとするのも間違い
読み上げるのがNGならやっぱり暗記するしかないってことか
予め決めた内容を覚えることで、話し方を安定させることは必要ですが、それは一言一句を暗記するということではありません。
むしろ、プレゼンで話す内容を一言一句まで暗記することは弊害の方が多いと思います。
なぜなら、プレゼンは計画通りに進まないことが多いからです。
例えば、
・出席予定者が遅れて参加してきたり
・説明している途中で質問されたり
・緊張して覚えた内容が飛んだり
・技術的なトラブルでプレゼンが中断したり
・予定していた時間がクライアント都合で短くなったり
するなど。
それにも関わらず、一言一句を間違わずに話すことを前提に準備してしまうと臨機応変な対応が難しくなってしまいます。
暗記したことがあだになって逆にパニックになるかもな
覚えるべきは各スライドの要点であり、スライドを見れば話す内容をなんとなく思いだす程度にしておけば問題ありません。
「テキトーに話す」といえば聞こえが悪いですが、適当の本来の意味である「ほどよく」という意味で、事前に決めた内容を概ね同じように話せれば問題無いということになります。