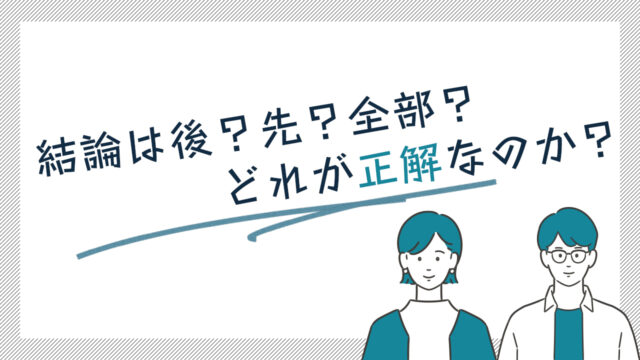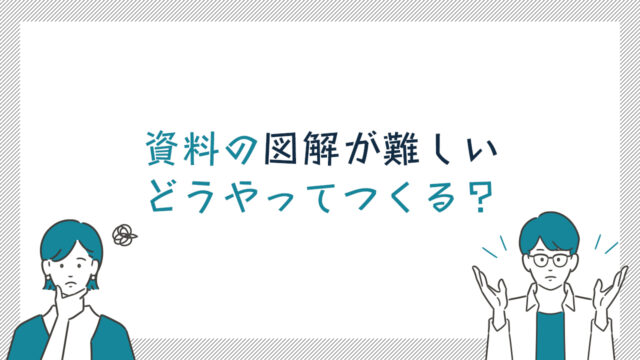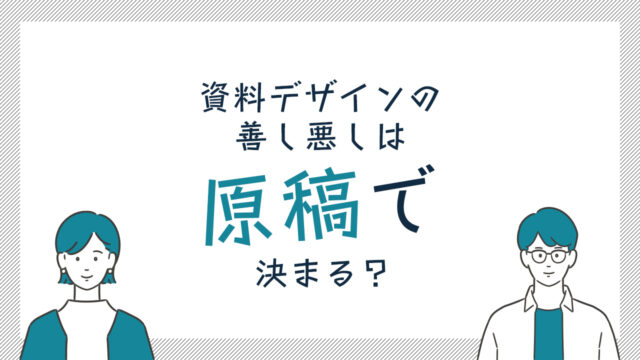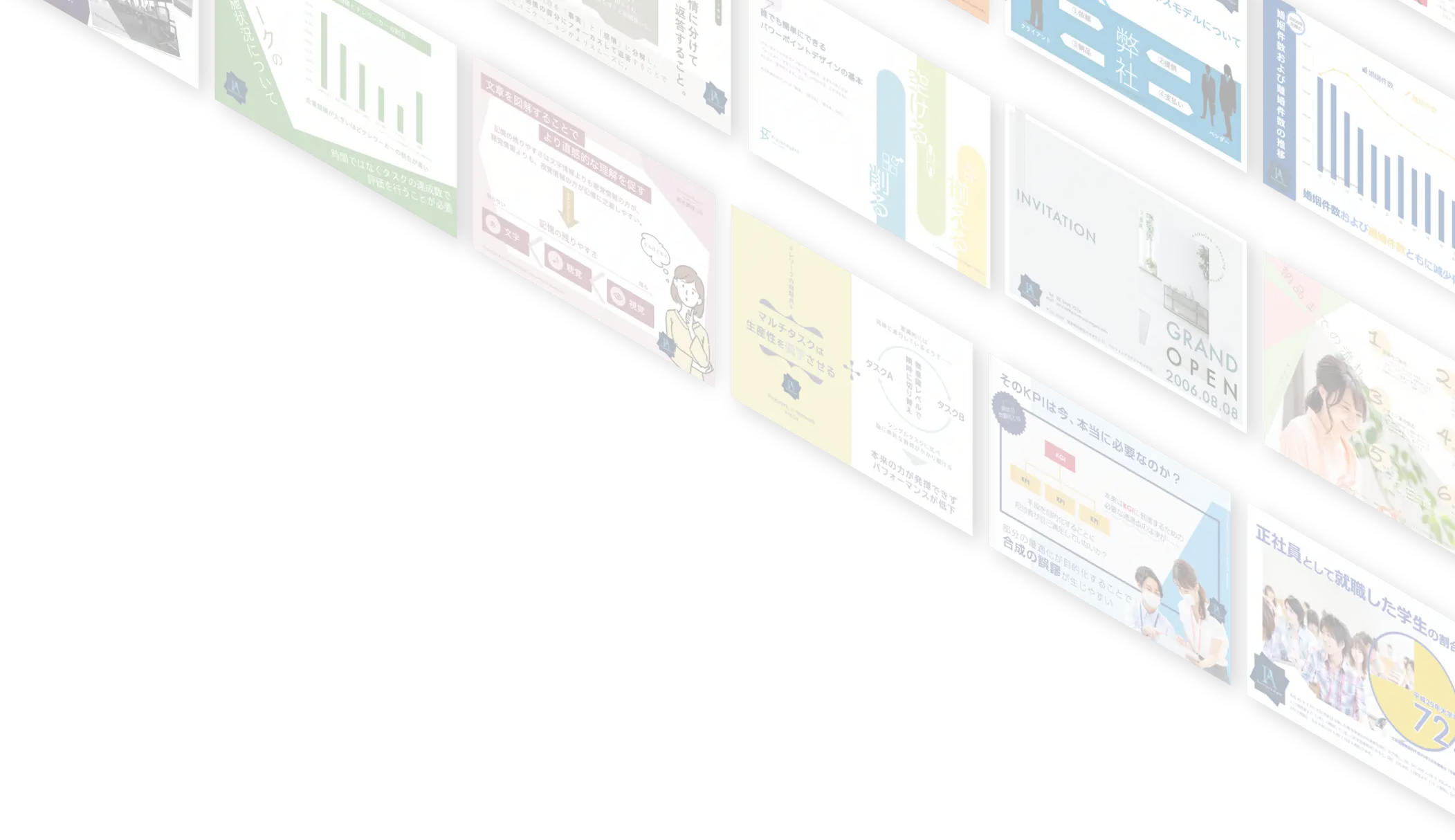

プレゼン資料づくりは
何から始めるべきか?
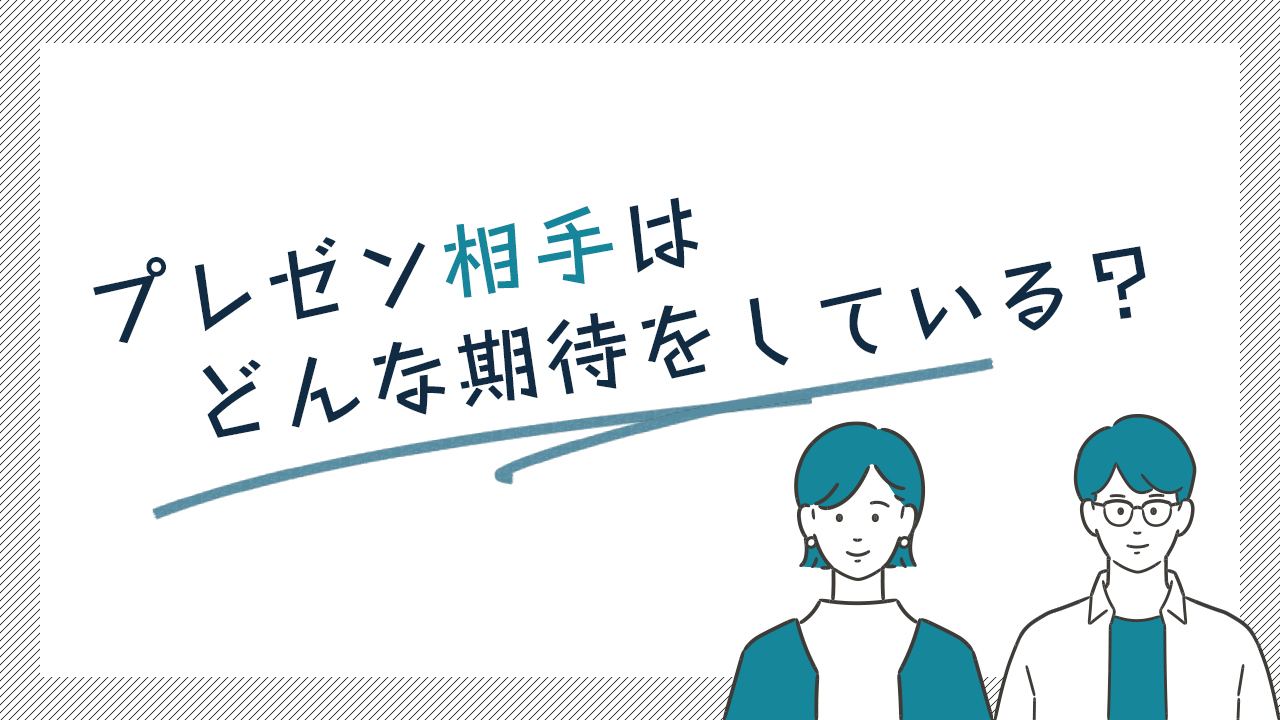
記事の内容
「誰に」プレゼンするかを明確にする
プレゼン資料をつくり始めるにあたって、まずすべきことはプレゼンする相手を5つの条件で絞り込むことです。
そうすることで「どんな人」にプレゼンしようとしているのかを明確化します。
相手が誰で、その人がプレゼンする自分に対して何を期待しているのかが分からなければ、プレゼン内容を決めることができないからです。
それにも関わらず、資料をつくり始める時に「誰に」を曖昧にしたまま「何を」「どうやって」という部分に意識が向きがちです。
誰にって、だいたいクライアントとかでしょ
たしかにそうなのですが、当然ながらクライアントも一様ではなく、様々な人がいます。人の意思決定は経路依存なので、過去にどのような経験をしてきたかによって、未来の選択も変ることになります。
例えば、過去に同じようなサービスを利用して、失敗した経験がある人は、新たにプレゼンを受けることに消極的になりやすいですし、はじめてプレゼンを受ける人であれば、相見積などを増やして全体をできるだけ俯瞰しようとするはずです。
それぞれに対するプレゼンの方向性として、前者であれば、いかにリスクが少ないかに重点をおいて訴求する必要があり、後者であれば同業他社との差別化要因を特に強調する必要があります。
何にプライオリティをおくかは人それぞれだからな
また、マーケティングの世界に「ドリルを売りたければ、穴を売れ」という有名な言葉がありますが、これはドリルを求める人はドリルそのものが欲しいのではなく、何かに穴を開けたいと思っているということです。
つまり、その人が発する表面的な言葉を鵜呑みにするのではなく、本当の目的や欲求を理解しなければならないということになります。プレゼンを受ける人には、その人なりの動機があります。
仮に売上アップを目指すプレゼンをするとして、そのことをクライアントの誰もが望んでいるかといえば、そう単純ではありません。
事実、現状を変えることに不満だけど、会社の方針で立場上プレゼンに参加しなければならないという人も存在するからです。
表面的には売上を上げることに賛成しつつも、心の内では現状が改善されてしまうと困ると思っているような状態です。
このようにプレゼン相手のステータスをどのように定義するかによって、プレゼンの方向性がまったく変わることになります。
プレゼン内容だけを磨き上げより良い提案をすれば採用される、ということは決してありません。何を「より良い」とするかは相手が決めるものだからです。
「誰に」プレゼンするかによって使える言葉や概念が変わる
例えば「フィボナッチ」「MACD」「移動平均線」という言葉を、金融関係の人たちの前で使えば、「チャート」の話をしているのかなと理解してもらうことができます。
しかし、そういった人たち以外には、表現する上でどんなに適切な言葉であったとしても、意図的に避けるべきです。
どうしても使わざるを得ないのであれば用語解説を随時行っていくプロセスをプレゼンの中に組み込む必要があります。
業界の常識を当たり前のように言われても困っちゃうし
これは同じ内容を伝えるとしても誰に伝えるかよって使える言葉や概念が変わることを意味します。
例え話も同様です。
「底をうったと思ったのでエントリーしたら、数日後に底が割れたようなものです」といえば、金融関係の人であれば「あるある」と共感してもらえる可能性が高いです。
しかし、それ以外の人たちからすれば「?」となってしまう可能性が高く、プレゼンへの集中力を削いだり、理解を妨げる原因にもなります。
これらのことからも「誰に」をはじめに想定することが、いかに重要であるかイメージしていただけると思います。
このプロセスをおろそかにしてしまうことで、プレゼン内容の善し悪し以前に、そもそも伝わっていなかったという事態が発生することにもなりかねません。
同じ相手でもフェーズによって伝えるべき内容が変わる
通常、プレゼンには多かれ少なかれフェーズがあります。
ビジネスの現場でよくあるのが、
第一フェーズは、顔合わせと商品やサービスの概要を伝える段階。
第二フェーズは、お客様のご要望を組み入れてカスタマイズする段階。
第三フェーズは、生き残った同業他社との決勝戦。
など。
同じ相手にプレゼンするとしても、どのフェーズで行うかによって伝える内容が変わってきます。コミュニケーションが増えるごとに相手のニーズが明らかになってくるからです。
第一フェーズでは、相手のホームページなどから事前に得られる情報や、自分や自社の過去の経験をもとに条件設定を行います。
設定のコツとしては、デモグラフィック的な属性(30代、会社員、男性など)よりも、「そういう人いるよね」と感じられる人を定性的に想定した方が、イメージに幅をもたせることができます。
例)
自分で使う資料ならつくれるが、そのつくり方を部下にレクしなければならなくなった人 など
ピンポイントに設定しすぎるとハズレるリスクが高まるからな
第二フェーズ以降は、プレゼン相手から聞き出した情報をもとに、相手が何に重点を置いているのかを探り、その中からどこに焦点をあててプレゼンするかを決めます。
最初に設定した条件を微調整していく感じかな
そういうことです。
5つの条件を設定することに関する「5つ」という数字については、あくまで目安で絶対的なものではありません。
とにかく重要なことは「誰に」を想定しながらプレゼンを設計することですので、プレゼン相手の情報をできるだけ集めて条件設定を行います。
プレゼンの成否は相手のニーズをいかに汲み取れるかにかかっている
結局のところ、プレゼンの成否はこの段階で集める情報の質と、それをいかに精査するかによって決まるといっても過言ではありません。
誰にでも受け入れられる絶対的に優れたプレゼンは存在せず、プレゼン相手を軸とした相手にとって価値のある提案を目指す必要があるからです。
それにも関わらず、プレゼンする人の思いつきや簡単に得られる月並みな情報をもとにプレゼン内容を企画していくのであれば、結果も自ずと見えてくることになります。
月並みな情報からは、月並みな視点しか生まれず、結果的に月並みな提案になってしまう可能性が高くなるからです。
それだけならまだしも、月並みどころか相手の期待を見誤って的外れなプレゼンになってしまったら元も子もありません。
そういうのを期待してプレゼンを
お願いしたわけじゃないんですってやつ?
資料のつくり方を学ぶループから抜け出せない理由
まずはターゲットを明確化するってよく聞く話だよな
でも、いざ自分で作るとなるとなぜか実践できないんだよね
それは、資料の体裁を整えることに重点がおかれ、その場その場で得られた情報を使って対処してしまっていることに原因があります。
例えば、問題が多発するソフトウエア開発で、問題が生じる度にその場しのぎの対応を繰り返しても、根本的な原因究明や設計の見直しを行わない限り、本質的に問題が解決することはありません。
対処療法的に後手後手になっている状態だな
そのとおりです。
スライド資料の作成においても、必要なのは断片的なテクニック論ではなく、ゼロから完成に至るまでの体系的な知識です。
そういったスライド資料づくりを学ぶループから抜け出せないというお悩みを解決するために、本サイトの内容や研修でお話しさせていただく内容をコンパクトにまとめた無料の動画講座をUdemyで公開しております。

倍速再生で最短30分ほどでご覧いただくことでできます。
見づらくて分かりにくい資料になってしまう原因は何か?
それを改善する方法とは?
そういったことを俯瞰することで、ご自身のスライド資料づくりを見直すきっかけにしていただければと思います。